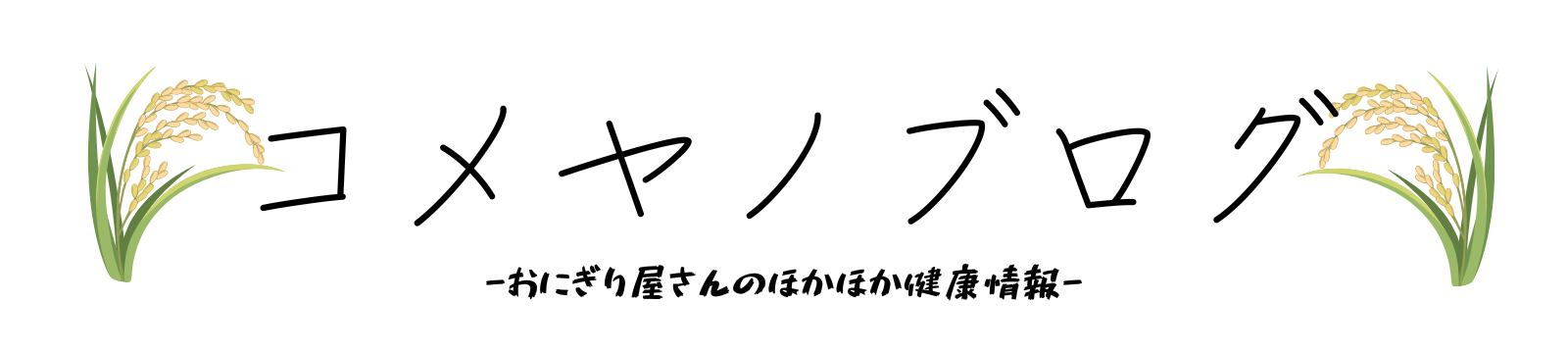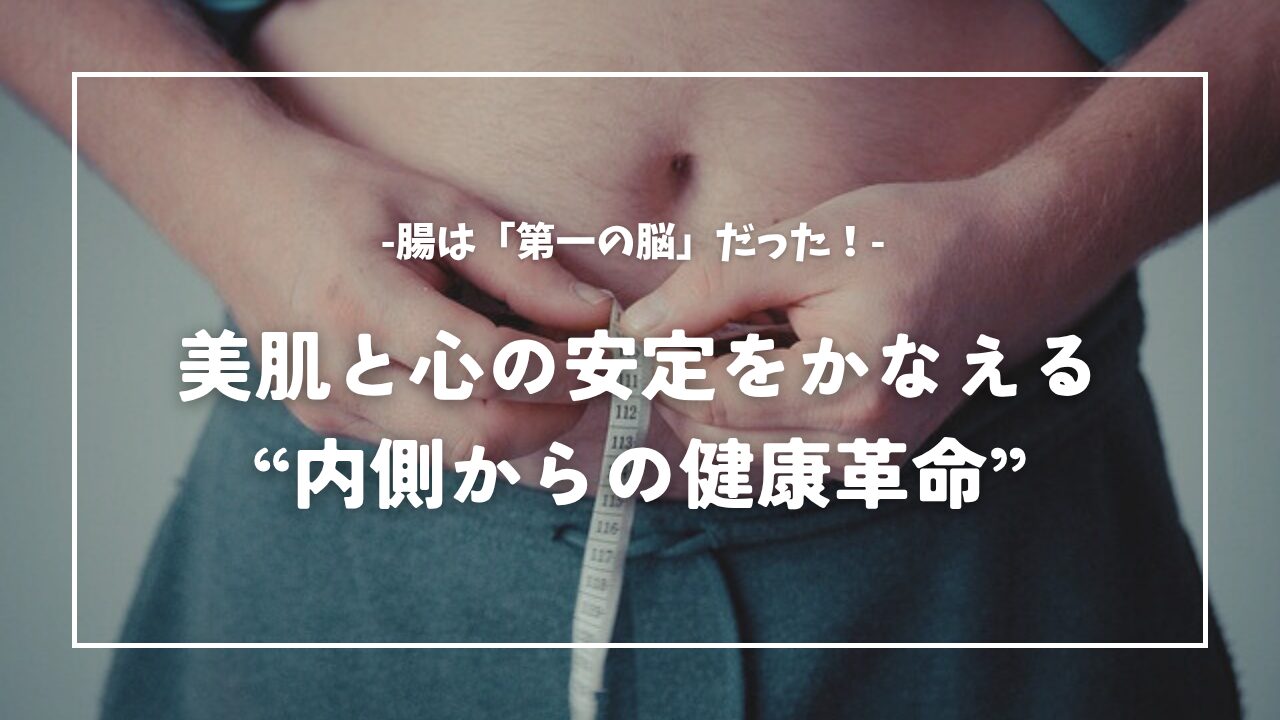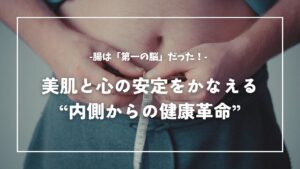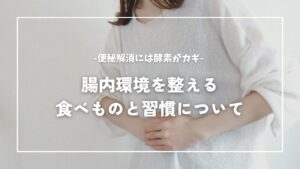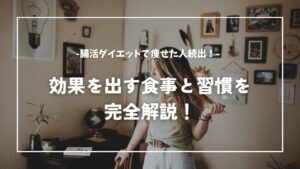こんにちは!村田おにぎりです!
今回のテーマは「腸が第一の脳と呼ばれる理由」についてです。
「腹が立つ」「腹を割って話す」「腑に落ちない」──
私たちは無意識のうちに“心(脳)”と“腹(腸)”を結びつける言葉を日常で使っています。緊張する場面でお腹が痛くなったり、旅行先で便秘になったりする経験はありませんか? 実はこうした反応は偶然ではなく、脳と腸が密接につながっている「脳腸相関」によるものです。
近年の研究では、腸は「第二の脳」ではなく、むしろ「第一の脳」と呼ぶべき存在であることが分かってきました。腸は消化だけでなく、免疫・ホルモン・メンタルバランスを司り、肌や体重管理、エネルギーレベルにまで影響を与えています。
本記事では、腸が「第一の脳」と呼ばれる理由を解説しつつ、忙しいライフスタイルのなかでも無理なく取り入れられる腸活のポイントや、美容・健康への具体的なメリットを紹介します。
「腸を整える=未来の自分への投資」。そんな新しい視点を今日から始めてみませんか?
腸は心の鏡 — 昔から使われてきた“腹”と心を結びつける言葉たち
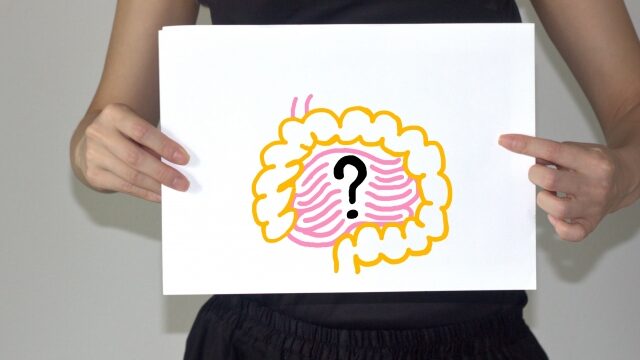
「腹が立つ」「腹を割って話す」「腑に落ちない」「腹の虫が治まらない」「太っ腹」──
私たちは日常のなかで、無意識のうちに“心(脳)”と“腹(腸)”を結びつける表現を使っています。これは単なる比喩ではなく、古くから腸と感情が深く関わっていることを経験的に知っていた名残ともいえます。
緊張するプレゼンの前にお腹が痛くなる、試験前に下痢をしてしまう、旅行先で便秘になる…
こうした現象は多くの人が体験したことがあるはずです。これは偶然ではなく、脳と腸が密接に情報をやり取りしている「脳腸相関」が背景にあります。
近年では、こうした心身の反応が科学的にも裏付けられ、腸は単なる消化器官を超えた“感情やストレスの鏡”として注目されるようになってきました。
つまり、昔から使われてきた「腹」をめぐる言葉には、私たちが感覚的に知っていた腸と心のつながりが表れているのです。
腸は「第二」ではなく「第一」の脳かもしれない

これまで腸は「第二の脳」と呼ばれてきましたが、近年の研究では「もしかすると腸こそ“第一の脳”ではないか」という見方が広がっています。
その背景には、腸が私たちの生命や感情、健康の根幹に深く関わっているという事実があります。
腸は、消化・吸収だけでなく、免疫システムの約70%を担い、血糖値や食欲をコントロールするホルモン分泌、さらには感情に関わる神経伝達物質の生成まで、多彩な役割を果たしています。脳や神経がまだ発達していない新生児期でさえ、腸は自らの判断で消化・排泄を行える“自律性”を持っています。
さらに、進化の過程を見ても、クラゲやイソギンチャクのように「腸はあるが脳はない」生き物が存在します。これは、腸こそが生命の起源であり、脳はその“出先機関”として後から発達した可能性を示唆しています。
こうした事実から、腸は単なる消化器官ではなく、全身の司令塔として私たちの体と心を支配する“第一の脳”と言っても過言ではありません。
私たちの体は「腸」から作られる

私たちの体は受精卵の時点から「腸」を中心に形づくられていることをご存じでしょうか?
受精卵の外側がくぼみ、その口が閉じて「腸」が形成され、そこから伸びて「口」と「肛門」ができます。その後、栄養をためる「肝臓」や酸素をためる「肺」ができ、さらに上部が膨らんで「脳」になります。
つまり脳は、腸の働きを補う“出先機関”として発達してきた可能性があり、「腸こそ生命の起源」という考え方が生まれたのも納得できますね。
進化の過程でも、クラゲやイソギンチャクのように脳のない生き物には腸が存在しますが、腸のない生き物はいません。これは、生き物にとって腸がいかに基本的で重要な器官かを示す証拠です。
腸は、私たちが生まれる最初の段階から命を支える“根幹”の臓器。
この事実を知ると、「腸を整えることは、体全体の健康を整えること」というメッセージが、よりリアルに感じられるはずです。
腸は独立した神経系を持つ

腸には、脳に次いで1億個以上の神経細胞が存在していることがわかっています。これは脊髄や末梢神経系より多く、脳からの指令がなくても消化・吸収・排泄などの機能を自律的に行うことができる“独立した神経ネットワーク”です。
例えば、生まれたばかりの赤ちゃんの脳はまだ未熟ですが、腸は自らの判断で栄養を消化し、便を排泄することができます。これは腸が脳に頼らず独自に働けることの証拠です。
こうした自律性を持つため、腸は「小さな脳」とも呼ばれます。近年の研究では、腸の神経ネットワークが脳とは別の判断を下し、私たちの健康や気分、食欲に影響を及ぼしていることも明らかになっています。
つまり腸は、脳からの命令を待たずに動ける“独立した司令塔”であり、ここに「腸は第一の脳」という考え方の大きな根拠があるのです。
参照:一色出版
腸が脳に感情や性格のサインを送っている

腸と脳をつなぐ太くて大きな神経「迷走神経」。この神経の繊維の約90%は、実は腸から脳へ情報を運んでいることがわかっています。つまり、脳が腸に指令を出しているだけでなく、腸こそが脳に膨大な“感情の素材”を送り届けているのです。
その代表例が、感情や性格を左右する神経伝達物質。たとえば、
- セロトニン(幸せホルモン):体内の約90%は腸に存在。腸内環境が乱れると減少し、便秘や気分の落ち込みを引き起こすことがあります。
- ドーパミン(快感ホルモン)・ノルアドレナリン(ストレスホルモン):腸内細菌と協力しながら合成・調整され、感情やモチベーションに影響を与えます。
このように、腸を整えることは心や感情の安定にも直結します。腸内細菌のバランスを良好に保てば、ストレスや不安のコントロールがしやすくなり、ポジティブな気分を維持できる可能性が高まるのです。
腸内環境が美容・健康に与える3つのメリット

① 美肌・透明感アップのメカニズム
腸内環境が乱れると、ビタミンやミネラルなど美肌に必要な栄養素の吸収が妨げられ、肌荒れやくすみの原因になります。
一方、腸内細菌のバランスが整うと、ビタミンB群やビタミンKなど肌のターンオーバーをサポートする栄養素がしっかり吸収され、透明感のある肌へと導かれます。
② 代謝・体重管理のサポート
腸内細菌は、私たちの代謝や脂肪の蓄積にも影響しています。腸内環境が良好だと、血糖値や食欲を調整するホルモン(インクレチンやGLP-1など)の分泌がスムーズになり、食べ過ぎを防ぎ、太りにくい体質づくりを助けてくれます。
③ ストレス耐性・エネルギーレベル向上
腸内環境は「幸せホルモン」セロトニンの生成にも関わっており、腸を整えることでストレスへの耐性が高まり、気分の安定や集中力アップにもつながります。結果として、仕事やプライベートでのパフォーマンスが向上し、毎日をもっとアクティブに過ごせるようになります。
このように腸は、美容・体重管理・メンタルヘルスという3つの側面を同時に支える“内側からの美と健康の要”です。
忙しい日々のなかでも、腸を整える習慣を持つことが、あなたの理想のライフスタイルを実現する近道になります。
忙しくてもできる!腸活を取り入れる3つのポイント

① 朝食やスムージーで発酵食品・食物繊維を簡単にプラス
朝のスムージーにヨーグルトや甘酒を加えたり、納豆やキムチを常備菜にしたりするだけでも、腸内の善玉菌を増やしやすくなります。
オーガニックスーパーで手に入る食材を組み合わせれば、毎日変化を楽しみながら続けられます。
② 時間がない日でもできる“ながら腸活”習慣
仕事の合間やヨガ・ピラティス前後に、軽くお腹をマッサージしたり深呼吸したりするだけでも、腸の蠕動(ぜんどう)運動を促すことができます。
ストレスを和らげつつ腸の働きを整えるので、リラックス効果とダブルでうれしい習慣です。
③ 自分に合ったサプリ・発酵食品の選び方のヒント
市場にはさまざまな腸活サプリや発酵食品がありますが、続けるには「味・価格・入手のしやすさ」などライフスタイルに合ったものを選ぶことが大切です。
まずは1種類を数週間試してみて、体調や肌の変化をチェックしながら自分に合ったものを見極めましょう。
忙しい毎日のなかでも、“ちょっとした工夫”で腸活は続けられます。
完璧を目指すのではなく、小さな習慣を積み重ねることが、腸内環境を整えるいちばんの近道です。
SNSや友人にシェアしたくなる腸活アイデア
腸活は、ひとりで続けるよりも“共有”することで楽しさやモチベーションがアップします。ここでは、SNSや友人にシェアしやすく、見た目にも映える腸活アイデアをご紹介します。
① 続けやすい“映える”腸活レシピ例

発酵フルーツスムージー(ヨーグルト+季節のフルーツ+チアシード)

彩り豊かな発酵野菜ボウル(納豆+キムチ)

腸活おにぎり(雑穀米+漬物や味噌で腸内環境サポート)
② コミュニティでモチベーションを維持する方法
- 腸活仲間とLINEやインスタグラムで「#腸活チャレンジ」や「#腸活1週間」などのハッシュタグを使って投稿
- 作ったレシピや感想、体調の変化をシェアする
- お気に入りの発酵食品やサプリを紹介し合う
腸活は、“ひとりの習慣”から“みんなで楽しむ活動”に変えることで、より続けやすく、効果を実感しやすくなります。今日からあなたも、ちょっとした腸活の工夫をシェアしてみましょう😊
まとめ|腸の声に耳を傾け、内側から整える
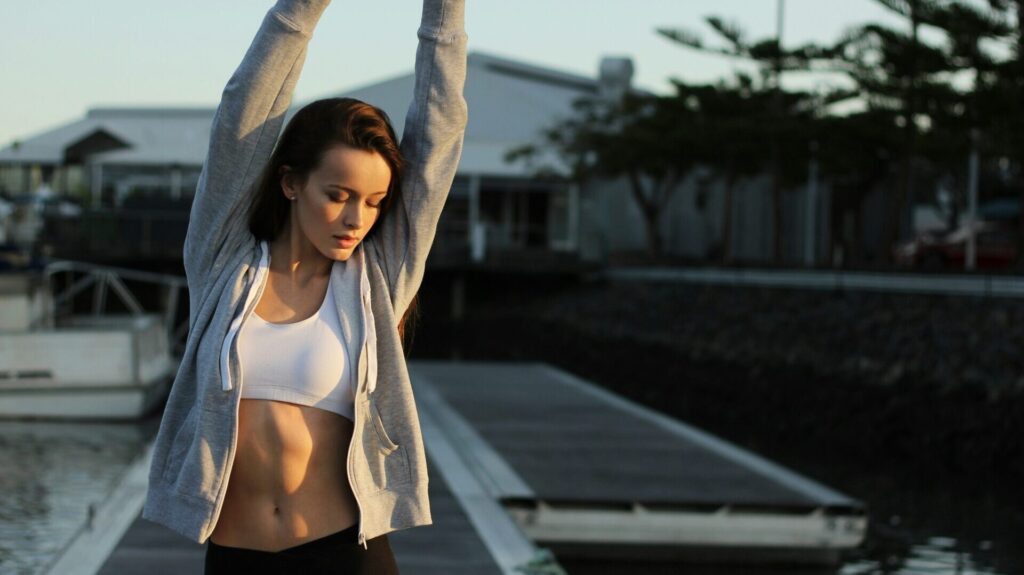
ここまで見てきたように、腸は単なる消化器官ではなく、免疫・ホルモン・メンタルバランスを司る“第一の脳”ともいえる存在です。
昔から“腹”と心を結びつける言葉が多く使われてきたのも、脳腸相関を経験的に知っていたからかもしれません。
腸を整えることは、
- 美肌・体重管理・エネルギーアップといった美容・健康メリット
- ストレスや感情の安定、集中力の向上といったメンタルメリット
- 免疫力向上や病気予防といった全身の健康メリット
など、私たちが望む“理想の自分”につながる最もシンプルな習慣です。
まずは1週間の腸活プランや、朝のスムージー、発酵食品など、できることから始めてみましょう。そしてその成果やレシピをSNSでシェアすることで、仲間と楽しみながら続けられます。
腸の声に耳を傾け、内側から整えることが、あなたの未来の健康と美容への投資になります。今日から“第一の脳”である腸を意識して、日々の生活に腸活を取り入れてみませんか?