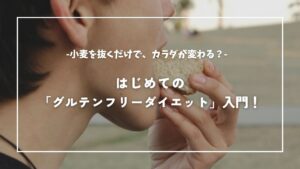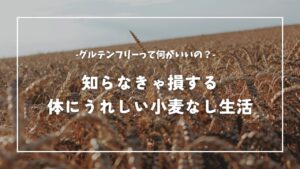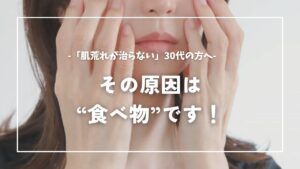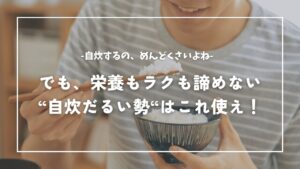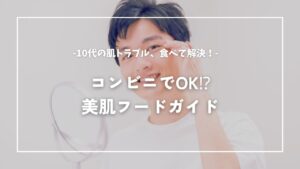「しっかり寝たはずなのに疲れが取れない…」そんな経験はありませんか?
それは、睡眠の質が低下し、深い眠りに入れていない可能性があります。
浅い眠りが続くと、疲れが抜けにくくなるだけでなく、集中力の低下や肌荒れ、自律神経の乱れなどの不調を引き起こします。
この記事では、浅い眠りの原因や改善方法について詳しく解説します。毎日の生活習慣や食事を見直して、ぐっすり眠れる体質を目指しましょう。
浅い眠りとは?深い眠りとの違い

眠りには「レム睡眠(浅い眠り)」と「ノンレム睡眠(深い眠り)」の2種類があります。
- レム睡眠:脳が活発に動いている状態で、夢を見ることが多い。
- ノンレム睡眠:脳も体も休息する深い眠りの時間。
本来、睡眠はレム睡眠とノンレム睡眠をバランスよく繰り返します。しかし、ストレスや生活習慣の乱れによって、ノンレム睡眠が減り、レム睡眠の割合が増えると「浅い眠り」の状態になります。
浅い眠りが続くと、疲労が抜けにくくなり、日中の眠気や集中力低下を招くため、改善が必要です。
浅い眠りの主な原因

ストレスや自律神経の乱れ
ストレスが多いと交感神経が優位になり、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。特に、仕事や人間関係の悩み、プレッシャーなどが慢性的に続くと、自律神経が乱れ、夜になってもリラックスできない状態が続いてしまいます。また、ストレスが原因で夜中に目が覚めやすくなることもあります。
寝る前のスマホ・ブルーライト
スマホやパソコンのブルーライトは、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を抑え、深い眠りを妨げます。特に、寝る直前までスマホを見ていると、脳が覚醒状態になり、スムーズに眠れなくなることがあります。
SNSのチェックや動画視聴が習慣化している人は、就寝1時間前にはスマホを控えることが大切です。
食事の影響
カフェインやアルコール、糖質の多い食事を寝る前に摂ると、交感神経が刺激され、眠りが浅くなります。特にカフェインは摂取後数時間にわたり覚醒作用が続くため、夕方以降のコーヒーや紅茶は避けた方が良いでしょう。
また、アルコールは寝つきを良くするように感じますが、実は睡眠の質を下げる原因になります。糖質の多い食事も、血糖値の急激な変動によって夜間の目覚めを引き起こす可能性があります。
生活習慣の乱れ
不規則な生活リズムや運動不足は、体内時計を狂わせ、睡眠の質を低下させます。特に、夜更かしや昼夜逆転の生活を続けていると、体内時計が乱れ、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因になります。
また、運動不足によって日中に十分な活動ができないと、夜に眠くなりにくくなり、睡眠が浅くなることがあります。適度な運動を取り入れることも大切です。
浅い眠りを改善する生活習慣

寝る前のリラックス法
- 深呼吸やストレッチで副交感神経を優位にする。
- 温かい飲み物(カフェインなし)を飲む。
- 寝る1時間前からスマホを控える。
適度な運動を取り入れる
- 朝や日中に軽い運動(ウォーキング・ヨガ)をすると、夜の睡眠が深くなる。
理想的な睡眠環境を整える
- 部屋の温度は20〜25℃、湿度は50〜60%に。
- 寝具は自分に合ったものを選ぶ(枕やマットレス)。
寝る時間と起きる時間を一定にする
- 体内時計を整えるために、毎日同じ時間に寝起きする。
また、睡眠不足を改善するのに役立つ食事法についても以下にまとめてありますので、こちらの記事もぜひ併せてご覧ください!

浅い眠りを防ぐ食事のポイント

ぐっすり眠れる栄養素と食べ物
- トリプトファン(大豆製品、乳製品、バナナ):睡眠ホルモン「メラトニン」の材料。
- マグネシウム(ナッツ、ほうれん草、玄米):神経の興奮を抑える。
- GABA(発酵食品、トマト、玄米):リラックス効果があり、寝つきを良くする。
避けたほうがいい食べ物・飲み物
- カフェイン(コーヒー、紅茶、エナジードリンク):交感神経を刺激し、眠りを浅くする。
- アルコール:寝つきは良くなるが、睡眠の質を低下させる。
- 砂糖が多いもの:血糖値の乱高下で眠りが不安定に。
まとめ

浅い眠りは、ストレスや生活習慣の乱れが原因で起こります。改善するには、
- 寝る前のリラックス習慣を作る
- 運動や睡眠環境を見直す
- 眠りをサポートする食事を意識する
といった工夫が大切です。
今日からできる小さな改善を積み重ねて、ぐっすり眠れる生活を目指しましょう!
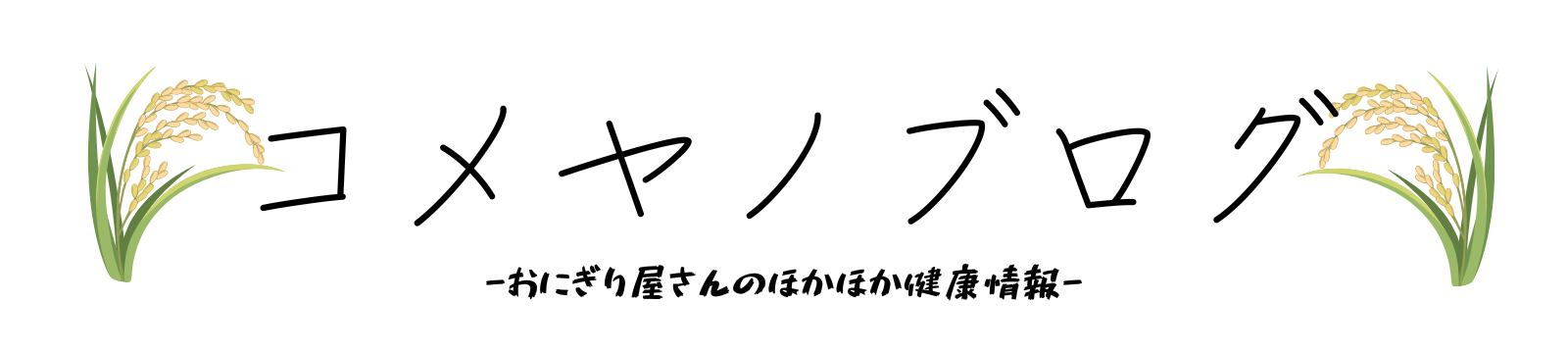

-300x300.jpg)